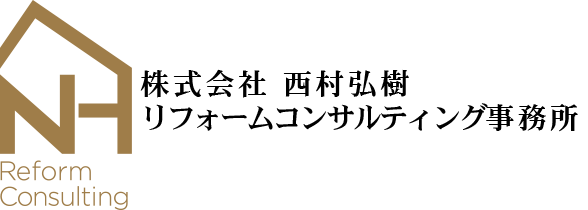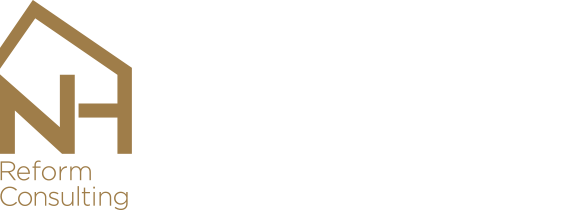2世帯住宅リフォーム
成功への4つの条件
2世帯住宅リフォーム
成功の4つの条件
親世帯と子世帯で異なる
価値観による問題の解決
異なる生活様式の家族形態が一つの建物空間で暮らすためには、多くの調整やそれぞれの家族への配慮が必要になります。2世帯住宅リフォームにはそのためのプランニングが必要になります。
将来発生する
問題を事前に解決
リフォームの後に実際に住んでみるとリフォーム工事の完成当時には想像もしていなかったような問題が発生します。この先に起こり得るそれらの解決策を事前に講じておく必要があります。
FP(ファイナンシャルプランナー)が
解決する資金計画の問題
とても大切な資金計画においては、有利な公的資金や補助金の活用、また、贈与税や相続税対策などを考慮した無理のない資金繰りが必要です。
過去の天災(地震等)を教訓にした、
現在の建築基準法以上の地震対策
リフォーム工事による構造上の問題点やその他の問題のある個所などの様々な問題解決に向けて、また建築基準法以上の地震対策を同時に行う必要があります。



2世帯同居のパターンをご存知ですか?
まずは、住宅リフォームを計画する住宅のパターン
A)子世帯が現在住んでいる住宅は売却し、現在親世帯が暮らしている家を高齢化した親世帯と子世帯が同居するために2世帯住宅リフォームを行う。
B)子世帯の住まいを、高齢化した親世代を引き取るために2世帯住宅リフォームを行う。
C)賃貸生活をしている子世代が、親の暮らす住宅に同居するために2世帯住宅リフォームを行う。
2世帯住宅リフォームの種類
1. 完全分離型2世帯住宅リフォーム。
2. 部分共有型2世帯住宅リフォーム。
3. 同居型2世帯住宅リフォーム。
2世帯同居のススメ!(2世帯同居を成功させるには!)
夢の実現のお手伝い。
1. 2世帯の双方にメリットいっぱいの、娘夫婦との2世帯同居。
2. 2世帯住宅は、自立した2世帯が住む家をつくる。
干渉しすぎず、無関心にならず、お互いが自立できる良い距離感を保つ心構えと、少しの空間工夫とそこに適した建築材料の選択が大切です。
3. 庭先別棟住宅は、プライバシーが確保できます。しかし現在、国が行っている2世帯住宅のメリットが受けられません。
4. 相続対策は最重要ポイント、2世帯住宅リフォームを最大限に活かした手続きをする為に行うこと!
・親の考えや希望を最優先とする。
・兄弟間の不平等の確認、解消が必要。
・リーダーシップをとって話合い。
・兄弟姉妹の現状生活を把握し、将来の姿も考える。
・話し合う事で、自己防衛にもなる。
・2世帯同居の兄弟からの許可は、そのまま財産放棄と結びつかない。遺産相続時にどうするかの話合いをし、最悪の事態(住宅ローンを残し、また土地建物をも失うこと)を想定した結論。
・不動産財産を分割するような計画は避けたい。
・生前贈与などに関して、お互いに認識しておく必要が有る。
・「うちはそんな財産が無いから、相続対策なんて必要ないだろう。私が死んだら仲良く分け合えばいい」
上記のような様々な考え方がありますが、実は思ってもみないような様々なトラブルがでてきます。たとえ仲が良い家族でも相続が起きると何らかしらのトラブルが生じますし、また、相続財産が少ない方がトラブルになりやすいという統計も有ります。
話し合いのポイント
話し合いをする際のポイントとして以下の3点があります。
① 方向性を確認しあう。
誰と「配偶者・両親・兄弟姉妹・同居しない配偶者の親」
何を「両親と住みたい気持ち・介護の分担・お墓の継承」
② 財産(生前贈与も含め)の把握をする。
「不動産(土地・建物)・預貯金・金融資産・株等・保険」
③ 関係者全員で以下の対策を立てる。
「親の世話と介護の方法・兄弟姉妹への平等」について。
5. 2世帯同居における争わないために必要な対策は?相続対策の第一優先は家族円満。
・人の持つ「感情」への対策
・財産の相続対策
まずは、相続財産の把握、全体を把握し、分析し、最終ゴールを目指す。
6. 誰に相談すべきか?(解決策は必ずあるはず)
・安易に税理士に頼るのではなく、建築知識や不動産の知識等も備えた専門家に相談すべき。
7. 話し合った内容を必ず書面で残す。
年月が経過した後でも確認ができるようにする。
2世帯同居の心得、親世帯の思い・子世帯の思い
理想はサザエさん一家?
アンケートから分析した、それぞれに合った2世帯同居の方法と同居のメリット
1、日常生活における協力で得られる3つのメリット
① 育児協力 → 主に親世帯から子世帯へのサポートですが、「孫と接する機会が増えた」、又は「親孝行ができた」といったメリット。
② 家事協力 → 親世帯と子世帯それぞれの都合に合わせた双方へのサポート。
③ 介護協力 → 親世帯を心配する子供の不安を解消。基本的には介護ではなく見守りの気持ちで「状況の把握」と「介護サービスのマネジメント」そして話し相手として接することができお互いのメリットとなる。
2、何かあったら協力、2世帯同居のありがたみは?
① 病気や出産時 → 二人目の妊娠中や体調を崩した時に、子供の世話や家事を手伝ってもらう。別居の親に介護が必要になる際のサポート。
② 旅行や出張、単身赴任
③ メンテナンスやトラブル対処
3、経済面
① 土地代がかからない
② 収入の増加と家賃相当分の有効活用
→親世帯のサポートで子育て期でも共働きが可能になり、ローンの返済能力がUP。
また、親世帯、同居の兄弟姉妹からの家賃で多少のゆとりのある生活が可能。
③ 光熱費の削減
→子世帯がローンを、親世帯が光熱費を支払うパターンも。同居の場合、基本的にはそれぞれの世帯で住むより光熱費や食費は安くなる。
④ 税金面の優遇
→2世帯ならではの税金面(相続)優遇の措置がある。
4、精神面、お金には換えられない精神面のメリット
① そばにいる安心感
→親世帯の安心感。(今後おこりうるであろう1人残された肉親へのケア)
→防犯上の安心感、2世帯住宅は担世帯の場合と比べ、被害リスクが半分というデータも。
② 孫の成長への好影響
→親子共に逃げ場があるということ。
③ 家族で共有する楽しみ
→それぞれの家族に触れる事により、世界が広がる。
デメリットとその対応策
1. 「見ざる、言わざる、聞かざる、そして困ったときは助け合う」
例えば、同居の子世帯のテーブルに朝食の食器がそのまま置いてあったとしても、それを洗ってはいけない。
これは、一度親切心からと思い食器を洗ってしまうと、以後お嫁さんは必ず食器を洗ってからでないと出かけられなくなってしまう。だから家の造り方で解決できることは解決する。
2. 元々家族ではない他人と同居することになる、これは結婚も同じはあるが夫婦とは別の気遣いが必要になる。お互いに歩み寄る。
3. 同居ならではのお互いの気兼ねや気苦労がある。歩み寄った会話が必要。
4. お互いの生活感と価値観の違いへの戸惑い。世帯間の協力が進むめばさまざまな形で相手からのサポートが得られる(2世帯同居における最大のメリット)
5. 感情のすれちがい。「孫の面倒を見てもらって当たり前、介護の世話をしてもらうのが当然」と考えがちですが、ありがとう・すみませんという言葉を口に出して言うこと。
6. お互いが同居初心者であり、初めから上手くいっている世帯は少ない、しかし10年過ぎたころからやっと根を下ろしたとおっしゃる方もいます。前向きな考え方で「2世帯同居は子供に良い影響を与えられる」と考えお互いが歩み寄って接する。
2世帯住宅リフォームの
メリットとデメリット
まずは、あなたの選択として、本当に2世帯住宅リフォームが必要なのかをご検討ください。
2世帯同居のメリット
子世帯のメリット
1. 子育ての事で頼る事ができる(子供への支援や面倒を見てもらえる)ので、共働きが出来る様になる。
2. 自力で持ち家は困難であったが、低コストで安定した住まいが確保できる。
3. 土地の購入費用が不要になり、経済的なメリット。
4. 家事の共有により、家族の時間を多く持てるようになる。
5. 親の老後の介護の心配の解消、親の様子がわかる。
6. 世代を超えた昔ながらの和やかな暮らしができる。
7. マナー、生活習慣、躾、思いやりなど、子供にとって、祖父母に学ぶことも多い。
8. 生活のルール(9時以降は静かに歩く等)を守る事で、社会人としてのマナーも身に着けられる。
9. 会話が多い子供は、会話が少ない子供に比べて、35%以上勉強に積極的という統計がある。
10. ちゃんと朝食を食べる子は、食べない子に比べて問題の正答率が高いという傾向がある。
11. 土地を確保して新築を建てるより、時間もコストも削減できる。
12. 人と社会のつながりを受け継ぐことができる。
13. 親世帯は自分の介護を他人に頼みたいようで、子供に自分の介護を希望していないケースが多いが、その際にもお互いの認識の共有とコミュニケーションが容易にできる。
親世帯のメリット
1. これから歳を重ねて行くので、一緒だと安心。
2. 孫といつでも会えるし、子供が近くにいる安心感がある。
3. 二つの住宅を持つより、コストがかからない。
4. 夫婦二人では広すぎる住まいの管理が大変だったし、寂しかった。
5. 老朽化した家をリフォームしたくても年齢的にローンを組むのが難しかった。
6. 孫の子育てを協力できる。
7. 孤独死を避けられそう。
8. オレオレ詐欺など、劇場型詐欺被害の被害から逃れられる。
9. 認知症の発生率が8分の1に!認知症の予防にも効果的であることが立証されている。
10. 病気、ケガなどの際に安心できる。
11. 防犯上の安心感がある。
12. お互いの様子が良くわかる。
親世帯子世帯、共通のメリット
1. 2世帯住宅リフォームで、両世帯とも”安心感“をもてる。
2. 別々に住宅を建てたり、リフォームするよりも、コストを大幅に削減(仮設費の削減など、建築費を合理化)することができる。
3. 光熱費を削減(基本料金の削減など、ランニングコストの合理化)することができる。
4. 体調が悪いときなども、お互いに安心できる。
5. 親世帯、子世帯のそれぞれで住宅ローン控除の適応を受けられる。
6. おかずのお裾分けがもらえる。
7. 10年後、20年後に向けた親世帯に対するバリアフリー等の介護対策が施された2世帯住宅リフォームを行っておけば、40年後(将来)の自分達(子世帯)の介護に備えるという事にもつながる。
8. 相続税で、減税措置が受けられる可能性が有る。(小規模宅地による特例)
2世帯同居のデメリット
子世帯のデメリット
1. プライバシーが守れない。
2. 家事などのやり方や価値観が違うため、もめる要因になる。
3. 時間や食事など生活の違いを合わせるのが難しい。
4. 世代間のギャップ。
5. 将来、子世帯だけになると2世帯住宅でなくても良くなる。(ムダになる)
6. 相続税がかかる。
7. 親の相続で、兄弟ともめる事もある。
親世帯のデメリット
1. プライバシーが無くなる。
2. 一人になりたくても、なかなか一人になれない。
3. 夫婦でのんびり遊べない。
4. 子供に財産贈与したいけど、税金がかかる。
親世帯子世帯、共通のデメリット
1. 築年数が古い場合、耐震も心配なので、2世帯住宅リフォームができるか心配。
2. 2世帯住宅リフォームは、大掛かりな改修工事が必要になり改修費用が掛かってしまう。
3. 世代間に格差が有り、価値観が異なるため、対立してしまうことが有る。
4. プライバシーの問題。
5. 生活スタイルの違い。
6. 親世帯が元気な時に2世帯同居にしたため、その後に介護が必要になるという更なるリフォームが必要になる場合がある。
7. 経済負担の偏り(生活費の分担の仕方をどうすれば良いのかの答えがわからない)
8. 2世帯分の収納場所が確保できない。
9. 同居していた親が亡くなってしまった。しかし、相続の際に現金財産が無く、せっかく作った2世帯住宅を取り壊し土地を売却し、財産分与として遺産を別けなければならないなんて、同居した時に想像もしてなかった。
10. 親の財産が、ほとんどこの家とこの土地しかない。また、土地の価格も高いので、兄弟との遺産相続がとても不安。
11. 同居するに際し、相続税対策が不安である。いざという時、どう相談したら良いのかわからない。
12. 2世帯住宅は、遺産相続を抜きにしては計画を進められないと聞いたが、どうしたら良いかわからない。
13. 一緒に住めない両親との関係が心配。
2世帯住宅リフォーム
お客様の声
実例から「あなたの家族のケース」にあった施工実例はありますか?
幸せ2世帯住宅リフォーム
お客様の声
古民家再生 姉と妹夫婦の2.5世帯同居
お姉様の声:すきま風だらけだった家が、暖かい家に生まれ変わりました。
茅葺屋根の古民家でも耐震補強も出来たので、この先、安心して暮らしていけそうです。T.I様邸 中野市 50歳代(1,500万円)
耐震補助金工事 娘夫婦2世帯同居
ご主人の声:増築せずに2階に娘夫婦のLDと寝室と洗面トイレを配置してもらいました。
また、1Fの浴室も広いユニットバスに取り替てもらい、孫と一緒に入るのが楽しみです。耐震補助金の申請も無料でやってもらいました。K.I様邸 長野市 60歳代(1,500万円)
なき息子さんのお嫁さんとの2世帯同居
ご主人の声:息子亡き後、離れに住んでいた義理の娘。孫の独立をきっかけに母屋に一緒に住めるようにリフォーム。
水回りを全て新しくし、一番日当たりの良い部屋を娘さん用にリフォームしました。当然、耐震補強もお願いしました。S.O様邸 中野市 80歳代(1,000万円)
耐震補助金工事 娘夫婦・孫夫婦3世帯同居
お母様の声:お母さんの住宅介護と耐震補助金での工事の予定で工事を始めたのですが、娘の妊娠が発覚し、急遽3世帯住宅リフォームに変更となりました。介護保険申請書類も耐震補助金の申請も、こちらでは何もやらずに全て無料でやってもらえて助かりました。
M.O様邸 飯綱町 50歳代(600万円)
娘夫婦2世帯同居
お母様の声:急な階段を架け替えする工事の際に、2階の梁にシロアリの被害が発覚、直ぐに対応してもらい原因は既存の屋根からの雨漏れでした。屋根の葺き替えのついでで工事をしてもらい、追加料金は掛かりませんでした。工事をやって良かった。
T.K様邸 長野市 60歳代(1,500万円)
耐震補助金工事 息子夫婦2世帯同居
お父様の声:敷地内に結婚する息子夫婦のために離れを建築する予定でしたが、他県に住む娘から母屋の古民家をリフォームすることを勧められました。工事の相談をしたところ、建物に対するメリットだけでなく、相続税の面でも圧倒的に有利になる事を知りびっくりしました。なかったコンクリート基礎を全て新設し新築と同等以上の耐震性能で、しかも須坂市からの補助金ももらえました。
念願の薪ストーブをリビングに設置し、すきま風だらけだった家が、薄着で冬を過ごせる家に変わりました。おじいちゃんも、おかげ様で長生きできそうです。U.K様邸 須坂市 50歳代(3,000万円)
娘夫婦3.5世帯同居+美容室
娘さんの声:2階の大きな窓からの景色が自慢で、お客様を呼ぶのが楽しくなりました。仲良しの小学生の娘と息子の部屋は1つの部屋で、将来、2部屋に分ける様に設計してもらいました。しかも、キッチンの横を必ず通る位置なので、子供たちとの毎日の会話もしっかりできます。
将来の美容室の回収にも対応できるように設計してもらい、正直、こんなに素敵になるとは思いませんでした。K.K様邸 須坂市 30歳代(1,800万円)
息子夫婦2世帯同居
息子様の声:母親の了解を得られないまま工事をお願いしてしまい、結局、工事途中で大幅な設計変更をするようになってしまい、大変ご迷惑をかけてしまいました。
T.K様邸 須坂市 50歳代(2,500万円)
水回り、息子夫婦2世帯同居
お嫁様の声:2階に子供部屋と寝室をつくるリフォームと、水回りをやり変えるリフォームでした。
確認はしたのだけど、1612のユニットバスは小さかったのが後悔です。S.K様邸 須坂市 30歳代(500万円)
平屋→2階増築 娘夫婦との同居
ご主人の声:定年退職で空き家状態であった実家に戻る事に、娘夫婦も一緒に住むことになり平屋から2階建にする事に。最初は心配したけれど耐震性能も新築と同じにでき、確認申請や完了検査も何の問題も有りませんでした。
娘夫婦との2世帯なので、水回りは2階にトイレと洗面を付けるだけでOKでした。 父親が愛した和室をそのまま残すことが出来て良かったです。M.K様邸 松本市 50歳代(2,200万円)
息子夫婦完全2世帯住宅玄関共通
お嫁様の声:2階を一部屋増築して、完全2世帯住宅リフォームを行いました。確認申請を出さなくても良い10㎡未満の増築でしたが、将来用の子供部屋もしっかりと確保できました。
インターネットで探してきた施主支給品も気持ちよく対応してもらい助かりました。
お父様のお気に入りの純和風の雰囲気の外観を壊すことなく、2階に広いルーフバルコニーを作ってもらえたので、両世帯とも満足です。K.K様邸 長野市 20歳代(2,000万円)
建築指導課職員 娘夫婦2世帯同居
お父様の声:建築の専門家である婿殿が居たので安心してリフォームを進める事が出来ました。 浴槽を解体した際に柱がシロアリに食べられており、初めてシロアリを生で見る事が出来ました。
床下調査では判らない場所だったので、今回の工事で発見できてよかったです。 浴槽の工事範囲内であったため、追加料金も掛かりませんでした。 元々すぐそばのアパートに娘夫婦は済んでいてくれたのですが、一緒に住んでくれるとやっぱり安心できます。孫と一緒に犬の散歩をするのが楽しみになりました。H.K様邸 長野市 30歳代(1,500万円)
息子夫婦2世帯同居
ご主人の声:二人の息子にそれぞれの部屋を与える為に2階を一部増築し、雪下ろしに対応するための屋根と外壁のやり変え、雪対策用の玄関への風除室の新設、水回りの一新を行い、ほぼ新築になりました。 耐震補強もしっかりしてもらえたためか、前の道路を除雪車が通るたびに真夜中に目を覚まされてしまったのですが、今年は一回も起こされませんでした。 リフォームする事でこんなメリットがあるなんて思いもよらず、母も喜んでいます。
S.K様邸 信濃町 40歳代(2,000万円)
親子2世帯同居 途中中止
娘さんの声:母の知り合いの業者が行ったユニットバスと洗面所の工事に不満が残ったため、その業者をお断りした上で、キッチンとリビング、娘(孫)用の部屋のリフォームの工事と防蟻工事をお願いしました。 しかし、知り合いの業者をお断りすることを了解してくれたはずの母が、「これ以上私の家の工事を許さない」と言い出し、結局工事を中止してもらう事になりました。年寄りの事とはいえ申し訳なかったです。
U.S様邸 長野市 40歳代(500万円)
息子夫婦2世帯同居
お母様の声:最初は、今後の生活を、斜め隣に住んでいる妹夫婦と仲良く生活できるようなリビングを作るという目的のリフォームでしたが、別居していた息子の会社が倒産してしまい、急遽2世帯同居する事になってしまいました。2階にトイレと洗面所を増設する事でプラン的には問題解決しましたが、まさかこんな事になるとは予想していませんでした。直ぐに対応して頂き、ありがとうございました。
T.S様邸 長野市 60歳代(2,000万円)
息子夫婦2世帯住宅UB共通
息子さんの声:高校の先輩の工務店に2世帯住宅リフォームをお願いしていたのですが、駐車場スペースを利用した大規模増築のプランが出てきて、プラン的にも予算的にも困ってしまい相談しました。 考えて頂いたプランは、建物の横の駐車場部分に1間分だけ総2階で増築したプランで、確認申請は必要でしたが予算的にも問題ありませんでした。2階の子供部屋はロフト付きで、将来2部屋に分けられるような設計で、子供たちも大喜び、今は親子の遊び場にもなっています。
M.S様邸 須坂市 30歳代(1,800万円)
古民家再生 息子夫婦2世帯同居
息子さんの声:善光寺さんの門前町で道路面に土蔵(蔵)が有る、いわゆる、うなぎの寝床の様な敷地の奥の傾斜地に2棟が建てられている、ビフォアフターに出てきそうな建物配置でした。大手証券会社を定年退職するにあたり、横浜とのやり取りでしたが上手くまとめて頂きました。 門前町の雰囲気を壊すことなくリフォームすることが出来ました。
K.T様邸 長野市 80歳代(2,800万円)
古民家再生 息子夫婦2世帯同居
ご主人の声:2世帯同居にあたり、和室2部屋の畳替えと床のやり変え、奥の間の改修工事と耐震補強という内容でしたが、耐震補強のバランスを考えて設計してもらえた上、荷物の移動の時間も頂けたので、年より夫婦だけでもリフォームを無事、行うことが出来ました。
K.N様邸 飯綱町 70歳代(300万円)
娘親子2世帯同居
娘さんの声:昨年母が亡くなり、80歳で一人暮らしになった父の介護の必要性から、2階に私と2人の子供の部屋を用意し、1階をバリアフリーにし、父の部屋を、介護用ベットを置いても介護がしやすく暖かい部屋にするという目的のリフォームで相談しました。 プラン提案の中で不要な部分を減築する事で、介護の車が父の部屋に横付けする事が出来る様になり、一気に介護が楽になりました。工事プラン等の打合せの中で、親子の絆を深める事も出来た様な気がします。
K.T様邸 長野市 50歳代(2,000万円)
姉と妹夫婦+義理の父2.5世帯同居
お姉様の声:契約後から工事着工までの間に父が亡くなってしまい、契約後にプラン変更になってしまいました。妹夫婦とその子供たちとの同居となり、一気ににぎやかな生活になりました。
K.T様邸 長野市 40歳代(1,800万円)
耐震補助金工事 息子夫婦2世帯同居
ご主人の声:耐震補助金を利用して、LDKと寝室の工事をお願いしました。 みんなが集まれるLDKになり、プライバシーが守れる寝室にすることが出来ました。
H.T様邸 飯綱町 50歳代(500万円)
孫夫婦との2世帯同居
奥様の声:私の家の隣にある、老朽化した父親夫婦の家を回収し、娘夫婦と親夫婦との2世帯住宅リフォームをお願いしました。2階にトイレと洗面所を増設し、孫世帯が住む計画にしました。ピアノ教室も上手く配置してもらえました。リフォーム資金は私達が出すつもりでしたが、工事費を直接負担すると贈与税がかかると指摘され、回避することが出来ました。親夫婦も安心して暮らしているようです。ありがとうございました。
K.T様邸 長野市 50歳代(2,200万円)
娘夫婦2世帯同居
奥様の声:娘夫婦との同居が決まり、浴室・洗面所・LDKを使い易くリフォームしてもらいました。 勝手口を設置するだけでこんなに便利になるとは思いませんでした。効果的に2重窓を付ける事で、光熱費も安くすることが出来、暖かい家でワイワイとやってます。
Y.T様邸 長野市 50歳代(600万円)
平屋→2階増築 娘夫婦2世帯同居
娘さんの声:実家で一人住まいをしている母が心配で同居を決意しました。平屋なので2階を増築することが可能なのか心配しましたが、調査して頂いた結果心配ないという事で安心してお任せできました。 2階に寝室と子供部屋を2つ、広い洗面所とトイレを増築して快適に暮らしています。 確認申請を出し新築と同じ耐震性能なので、私の孫の代まで、100年安心できそうです。 固定資産税も増築した2階の分しか増えませんでした。
T.T様邸 長野市 30歳代(2,200万円)
娘夫婦2世帯同居
娘さんの声:もともと2世帯で住んでいたのですが、子供が大きくなったのでリフォームを考えました。 両親も気に入っている1間間口の玄関と廊下を見事に演出してもらえました。LDKとつづき間の和室も見事に復活して頂き、新築では出来ないような出来栄えに大喜びしています。
T.N様邸 須坂市 40歳代(2,500万円)
息子夫婦2世帯同居
奥様の声:老後に備えて、水回りの一新と、続き間付きのLDKと寝室のリフォームを行った所、リフォーム完了後に息子夫婦が同居することになりました。 この様なケースも珍しくないとお聞きしびっくりしました。
A.N様邸 千曲市 60歳代(800万円)
息子夫婦完全2世帯住宅玄関共通
ご主人の声:息子夫婦と同居にあたり、確認申請が必要なプランになったが、土地が旗竿地で接道部分の幅が2mは有るのだが半分は赤線であるのでこのままでは確認申請が下りないことが判明した。 困って相談したところ、赤線の買取交渉を役所と行ってもらい、近隣住民の承諾の手続きもやってもらえました。御社に出会えなければ、二束三文の土地のままで、2世帯同居は夢のままでした。 工事中も、妻からの変更が多く大変であったと思いますが無事市役所の検査も終わりました。苦労してもらいありがとうございました。
T.N様邸 長野市 30歳代(3,100万円)
古民家再生 息子夫婦完全2世帯住宅
ご主人の声:築85年でも、全く新築と変わらない出来栄えでびっくりしました。さらに、固定資産税も増築部分にしか課税されていませんでした。事前の説明通りでした。震度3くらいの地震では、全くと言って良いほど揺れは感じません。
H.N様邸 長野市 40歳代(2,500万円)
古民家再生 息子夫婦2世帯同居
ご主人の声:以前に浴室をリフォームした時の業者とのレベルの差にびっくりしました。 地震が心配だったので、耐震補強には満足しています。リビングも暖かくなり、母も喜んでいます。
Y.N様邸 信州新町 50歳代(1,500万円)
介護住宅リフォーム 息子夫婦2世帯同居
奥様の声:前面道路の工事での振動の影響で家の外壁にひびが入ったり屋根瓦がずれてしまった事をご相談したところ、長野市と折衝をして頂き、無事、補修費を受け取る事が出来ました。 屋根・外壁の工事に合わせ、以前から計画していた母親の介護のための屋内のバリアフリーとトイレの改修も一緒に行いました。介護保険の書類の対応もして頂きありがとうございました。
S.H様邸 長野市 40歳代(800万円)
古民家再生 耐震・太陽光発電補助金工事 息子夫婦2世帯同居
ご主人の声:西村さんに出会える前は、築240年の家はこのままにして離れにこじんまりとした家を建てる予定でしたが、様々なお話を聞いたり、実際の古民家リフォームを見せて頂いているうちに、母も妻も私も、古民家リフォームのとりこになってしまいました。 冬はすきま風が床下から吹き上げ、寒くて仕方がなかった古民家が、蓄熱暖房をご提案頂いたおかげで、冬でも薄着でいられる家に変わりました。耐震補助金の申請も太陽光パネルの補助金の申請も全て無料で行って頂きありがとうございました。
H.H様邸 須坂市 40歳代(5,500万円)
LDK 息子夫婦との完全2世帯同居
ご主人の声:古い床暖房の回収工事も嫌な顔をせずに行ってくれて助かりました。 細かな補修工事が多く大変だったと思います。
S.M様邸 長野市 60歳代(800万円)
息子夫婦2世帯同居
息子さんの声:当初家族で予定していたプランとは全く違ったプランになりましたが、住んでみると流石プロが考えたプランで、みんな満足しているようです。提案の中では、メリットだけでなくデメリットも教えて頂き、判断するのに迷いませんでした。
T.M様邸 須坂市 30歳代(1,800万円)
娘夫婦2世帯同居
ご主人の声:敷地が計画道路にかかっており家にお金をかけるのには躊躇していました。しかし、娘が結婚するのをきっかけに同居するという話が持ち上がりご相談することになりました。役所で調べて頂いたところ、我が家の部分の計画道路については「事業仕分け」で中止になっていると聞かされびっくりしました。家の状態を調べて頂いた結果も問題ないという事だったので、満足できるプランでリフォームする事に決めました。基礎補強工事も行った地震に強い新しい家につくった書斎でくつろいでいます。
S.M様邸 須坂市 50歳代(2,200万円)
娘夫婦と母、3世帯同居
ご主人の声:大人数が住みながらでの工事で大変でした。工期も若干遅れましたが出来栄えは満足しています。和室の上げ下げ障子は出来上がりを見て納得しました。玄関の式台の提案や片持ちの庇も、使い易く感謝しています。こんなに変わってしまうとは思いませんでした。 自分で行った庭の工事で、最後に庭土で困った際もすぐに用意してくれて助かりました。
K.M様邸 千曲市 60歳代(2,200万円)
息子夫婦2世帯同居
お母さまの声:一人暮らしの私を心配して、息子夫婦が一緒に住みたいと言ってくれてうれしいと思っていたら、あっという間に完成してしまいました。少し増築するだけでこんなに便利になるとは考えませんでした。広くなったお風呂に入るのが毎日の楽しみです。
J.M様邸 長野市 60歳代(800万円)
息子夫婦完全2世帯住宅玄関共通
お嫁さんの声:吹抜けをつぶして2階の部屋数を増やし、1階と2階と別けた完全2世帯にしました。2階の床下に遮音シートを張ってもらいましたが子供たちが騒ぐと下の家に響くそうです。ですが、孫が出す騒音は気にならない様で助かります。1階に作ってもらったピアノ教室も繁盛しています。
H.M様邸 長野市 30歳代(1,000万円)
水回り 息子夫婦2世帯同居
奥様の声:義母と同居するにあたり、地震が怖くてその道のプロに相談しました。水回りを新しくし、新潟に住むお母さんの部屋もリフォームして暖かくできたので、喜んで住んでくれていて主人も喜んでいます。
S.Y様邸 須坂市 50歳代(800万円)
娘夫婦2世帯同居
ご主人の声:80歳で一人暮らしの私を心配して、娘夫婦が同居を提案してきた時は断ったのですが、いざ一緒に住んでみるとこんなに安心できるとは思いませんでした。工事中も毎日のように顔を出して私の健康を気にして頂き感謝しています。近くに来たら寄ってください。
K.Y様邸 長野市 80歳代(1,800万円)
1億円超え、完全2世帯住宅+離れ 新築物件
ご主人の声:屋根はむくりを付け、母屋の他に、両親用の離れと、客室も離れに、元々あった土蔵は道路側に移築しました。保存樹林のケヤキを活かした植栽や取り囲んだ塀は、なかなか長野県では見られないセンスの良さだと思います。 工事中に父が倒れ、救急車を呼んでいただきありがとうございました。
S様邸 長野市 60歳代(1億円越え)